
こんにちは、名越凜です。
このブログは、四季折々にある日本の行事や日々の生活を愉しむコツをご紹介していきます。
私は、四季の行事など全く興味がありませんでした。それでも、何も支障はなかったのですが、結婚した後、子供の成長と共に色々なことを経験するたびに自分が何も知らないことを実感しました。このままでは、どれが正解なのかわからない。子供にきちんと教えることも出来ない。親として情けないと思い、少しずつ勉強を始めました。私が知らなかったように、もし知りたいと思っている人のきっかけになればいいなと思います。四季折々の日本の行事を愉しみましょう。
今回は、『恵方巻』についてです。
節分とは?

『節分』とは、「季節」を分けるという意味です。また、雑節の1つです。
本来、季節を分ける日は1年間に4回あって、春夏秋冬それぞれに始まりの日が決められています。
春夏秋冬、それぞれが始まる日の前日のことを『節分』といいます。しかし、太陽の動きによって決まるので、毎年同じ日とは限りません。
また、季節の変わり目には邪気(鬼)が生じると考えられており、その鬼を追い払い、無病息災を願う儀式です。
2025年は、2月2日(日)で、恵方は西南西です。 2026年は、2月3日(火)で、恵方は南南東です。
恵方とは?

『恵方巻』は、節分の日に食べる「巻きずし」のことですね。皆さんは『恵方巻』を食べますか?
『恵方巻』の恵方は、毎年変わりますが恵方とはどうして決まるのでしょうか?
恵方は、その年の十干(じっかん)で決まります。
暦注(れきちゅう)の多くは、陰陽五行説という古代中国の思想や易から発生し、月日に当てられるようになったもので、その大きな柱となるものが干支です。
※暦注(れきちゅう)とは、暦に記載されている吉凶や禁忌などの情報、いわゆる「今日の運勢」のような占いや迷信の一種です。
昔の暦には、日付や天文現象の予報以外に、日時の吉凶・禁忌などの迷信的な事柄が多く書き込まれていました。これを暦注といいます。日の吉凶、方位、六曜、二十四節気、雑節、干支、天象、潮汐などをいいます。
十干という言葉も、あまり聞き慣れませんね。
干支は、十干と十二支の組み合わせで出来ています。
十干とは、『甲・乙・丙・丁・戌・己・庚・辛・壬・癸』のことで、10日ごとに「一旬(いちじゅん)」と呼び、3つの旬(上旬・中旬・下旬)で1か月になるため、広く使われていました。
一方、十二支は、もともと12ヶ月の順を表わす呼び名でしたが、やがてこれらに12種の動物を当てはめるようになったものです。
2024年は、『甲辰(きのえたつ)』十干の「甲(きのえ)」×干支の「辰(たつ)」の組み合せです。
2025年は、『乙巳(きのとみ)』十干の「乙(きのと)」×干支の「巳(み)」の組み合わせです。 2026年は、『丙午(ひのえうま)』十干の「丙(ひのえ)」×干支の「午(うま)」の組み合わせです。
恵方巻を食べる時に今年の恵方(方位)を調べますね。
その方位にも決まりがあります。
- 甲・己の年 東北東やや東
- 乙・庚の年 西南西やや西
- 丙・辛・戌・癸の年 南南東やや南
- 丁・壬の年 北北西やや北
2024年の恵方は『甲辰(きのえたつ)』ですので、 「東北東やや東」 2025年の恵方は『乙巳(きのとみ)』ですので、「西南西やや西」 2026年の恵方は『丙午(ひのえうま)』ですので、「南南東やや南」
仕組みがわかると、納得できますよね。
恵方巻は、商売繁盛、無病息災、幸せを一気にいただく、などのご利益があり、恵方を向き、話もせず、一気に食べるのがおすすめです。
途中で止めたり、止めると運を逃すと言われていますので、私は食べ切れる大きさにしています。
まとめ

恵方は(吉方)は、歳徳神(年神)の来臨する方角で万福、食物、財宝の豊かな方角と考えられ、一年中の大吉方位とされています。
また、恵方とは、吉の方向または「塞がり」に対して「明き」方向を指す言葉でもあります。
つまり、明るい光の指す年神さまがいる方向を向いて食べることでご利益が得られます。
皆さんも恵方巻を食べる時に、吉方を意識したいですね。皆様にも、たくさんのご利益がありますように願っています。
最後まで読んで下さりありがとうございました。
『節分は福を招きます』も合わせて読んで頂ければ嬉しいです。
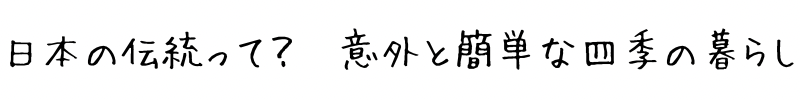

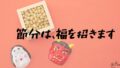
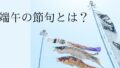
コメント