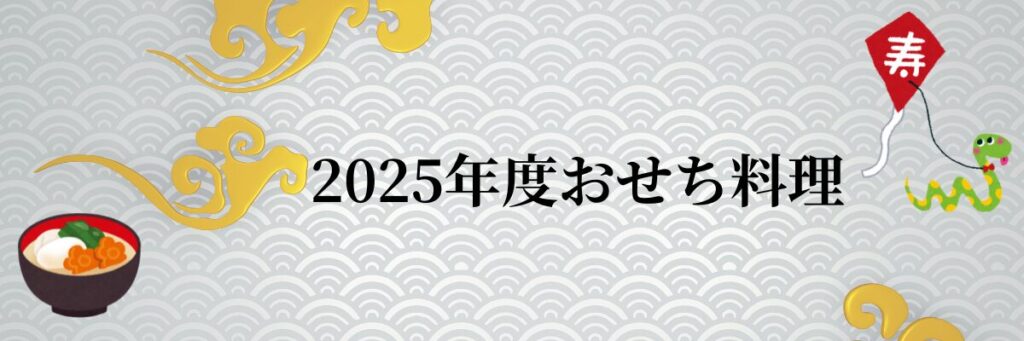
明けましておめでとうございます。名越凜です。
このブログは、四季折々にある日本の行事や日々の生活を愉しむコツをご紹介していきます。
私は、四季の行事など全く興味がありませんでした。それでも、何も支障はなかったのですが、結婚した後、子供の成長と共に色々なことを経験するたびに自分が何も知らないことを実感しました。このままでは、どれが正解なのかわからない。子供にきちんと教えることも出来ない。親として情けないと思い、少しずつ勉強を始めました。私が知らなかったように、もし知りたいと思っている人のきっかけになればいいなと思います。四季折々の日本の行事を愉しみましょう。
今回は、私の『おせち料理』をご紹介します。
我が家のおせち料理です。

簡単な説明をします。
一の重
- 田作り 鰯(いわし)を肥料にすると豊作になったことから、「五万米(ごまめ) 」とも呼ばれます。
- 数の子 卵が多いことから子宝に恵まれ、子孫繁栄を願います。
- 黒豆 健康でまめに働けるように、元気に暮らせるようにとの願いを込めています。黒は、魔除けの色でもあります。
- 栗きんとん 栗は「勝ち栗」と呼ばれる縁起物です。金団(きんとん)は、蓄財につながります。
二の重
- ニシンと菜の花の和え物 ニシンは、「子宝に恵まれる魚」です。菜の花は、「春を告げる」野菜です。
- 菊花かぶ 菊の花は「おめでたい」象徴です。菊花のように庖丁を細かく入れるのがポイントです。
- 黄金いか いかと数の子を和えたものです。おめでたい「黄金色」で、お正月に使われます。
- 金柑の蜜煮 「金冠」に通じ、財宝を意味し、金運を願った物です。
- かまぼこ 「加賀つづみ」金沢の蒲鉾です。花のように美しいです。
- 牛肉八幡巻き 細く長く、長生き出来ますようにと願いを込めます。
- 酢だこ 「多幸(たこ)」と漢字を当てることができるので「一年間幸せでいられますように」との願いが込められています。赤は魔除けの意味があります。
- 酢れんこん れんこんは穴が開いているので、将来を見通されるように、先見性のある1年を願います。れんこんは、花れんこんにしています。
- 紅白なます 紅白でおめでたく、平和、平安を願う縁起物です。
三の重
- ぶりの照り焼き ぶりは、出世魚です。立身出世を願います。
- 海老のうま煮 腰が曲がるまで、元気で長生きすることを願います。
- 伊達巻 文化の発展を願う縁起物です。
- 玉子焼き 子孫繁栄を願います。
- 紅白かまぼこ 紅白でおめでたく、半円形は日の出を象徴します。
- 鴨のロースト 良いことが重なり、ますます上手くいくことを願います。
- 煮豚 豚肉は、子孫繁栄や富と繁栄の象徴でもあります。
- 蟹 ハレの日の定番食材です。勝利や魔除けの意味もあります。
- ロースハム 豚肉は、子孫繁栄や富と繁栄の象徴でもあります。
- 若桃の甘蜜煮 種が硬くなる前の若いうちに採った桃を甘く煮詰めたものです。いつまでも若々しくいられるようにという願いが込められています。
- 干支かまぼこ その年ならではの縁起物です。

煮しめ 家族が仲良く過ごせますようにと願います。
- 鶏もも肉 子孫繁栄を願います。
- 里芋 ひとつの種芋にたくさんの小芋がつくことから、「子宝・子孫繁栄」の願いが込められています。
- 人参 「ん」がつくので運がつきます。にんじんを梅の花に見えるように飾り切りしたものを「ねじり梅」といいます。
- ごぼう 家の基礎がしっかりするように願いを込めます。
- れんこん れんこんは穴が開いているので、将来を見通されるように、先見性のある1年を願います。れんこんは、花れんこんにしています。
- しいたけ 「長生きできるように」という願いを込め、「亀の甲羅」のように六角形に飾り切りすることが多いです。
- こんにゃく 手綱をイメージして作られた手綱こんにゃくは、「良縁や夫婦円満」の願いが込められています。
おせち料理とは?
おせち料理は、神様にささげる料理である「お節供」が、変化したものです。
『五節供は、特別な日です』でも、ご紹介したように本来1月1日の元旦も本来は節句に含まれるべきですが、別格とされています。
お節供は、季節の行事の度におせち料理はお供えされていましたが、現在では、お正月だけ作られるようになり、おめでたい『ごちそう』のことを意味するようになりました。
色とりどりの料理には、さまざまな意味が込められていて、幸せが重なるように重箱などに詰められます。
新年を『おせち料理』で、華やかに彩るとともに、1年つつがなく暮らせることを願います。
筑前煮と煮しめの違いは?

おせちの煮物は、「煮しめ」または「筑前煮」が多いですね。煮物は、基本的には「三の重」にいれます。我が家では、三段重にはおせちを詰めて、煮物はお皿に盛ります。
おせちには、どちらを入れてもいいのですが、「筑前煮」と「煮しめ」の違いはご存知でしょうか。
大きな違いと言えば、具材を炒めるのか、炒めないかの違いです。
- 筑前煮 「筑前煮」は、もともと九州地方の代表的な郷土料理として親しまれており、その後全国的に有名になって、おせち料理として用いられるようになりました。また、「がめ煮」と呼ばれることもありますが厳密に言えば「筑前煮」と「がめ煮」は、別の料理です。共通点は、最初に油で具材を炒めてから煮込むことです。地域によって、名前や具材も異なりますが、福岡県の郷土料理「がめ煮」が、「筑前煮」のルーツとも言われています。
- 煮しめ 飾り切りで切った縁起の良い食材をゆっくり煮しめていく料理です。「煮しめ」という名前の由来は調理法の「煮しめる」からきています。「煮汁がなくなるくらいまで、時間をかけて煮る」という料理法が名前になっています
- 炒り鶏 「煮しめ」より、簡単に作ることが出来ます。具材は、飾り切りなどはせずに、手間をかけずに作ります。最初に炒めることで、短時間で煮込んでもコクが出ます。
私のお雑煮

私の『お雑煮』は、父から受け継いだものです。
私の実家では、女性は3が日は料理を作らないようにしていました。毎年、元旦の『お雑煮』は、父が作ってくれました。父の実家の味です。
具材は、鶏肉、白菜、紅白かまぼこ、餅のシンプルなものです。
豪華な晴れやかさはありませんが、丁寧にとった出汁の香りがいいすまし仕立てのお雑煮です。
さて、お雑煮の由来ですが、
お雑煮は、年末にお供えした「年神様」へのお供え物をその年の最初に井戸や川から汲んだ「若水」と合わせ、最初の火で煮込んで食べたと言われます。
『お雑煮』は、いろいろな材料を混ぜ合わせた汁物「煮雑(にまぜ)」や消化のよい餅やいろいろな具材を煮て食べ身体を健康にするもの「保臓(ほぞう)」とも呼ばれていたことが語源とも言われています。
『お雑煮』は、地域や家庭によっても様々です。代表されるのは、関東は角餅ですまし仕立て、関西は丸餅で白味噌仕立てと言われます。
おせち離れとも言われますが、元日だけでも1品だけでも、召し上がってほしいです。
まとめ

いよいよ2025年が始まりました。
皆さんにとっては、三が日はどう過ごされましたか?
現在では、年中無休で食材も買えますし元日でも外で食べることも出来ます。昔のよう『おせち料理』だけを食べていることも少なくなっているように思います。
それでも、私は『おせち料理』を作るのが好きで毎年作ります。ずっと、キッチンに立ち続けて、腰がいたくなったり、「来年は作らずに買おう」と思うのですが、1年経つとすっかり忘れて、買い物の準備を始めています。
それだけ慣例行事になっています。
元旦に一番食べたいと思うものは、やはり『お雑煮』です。毎年丁寧に出汁をとり、雑煮椀に入れて飲むときに一番新年を感じます。
『お雑煮』も皆さんご自身で作るのもいいですし、ご両親に作っていただくのも、お店で頂くのもいいと思いますが、ゆっくり味わる時間があればいいなと思います。
皆さんにとりまして、2025年が健やかでありますようにお祈りしております。
「おせち料理を作るためのポイント」と「2025年度お正月飾り」も一緒にご覧いただければ嬉しいです
最後まで読んで下さりありがとうございました。
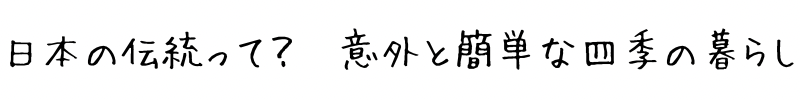
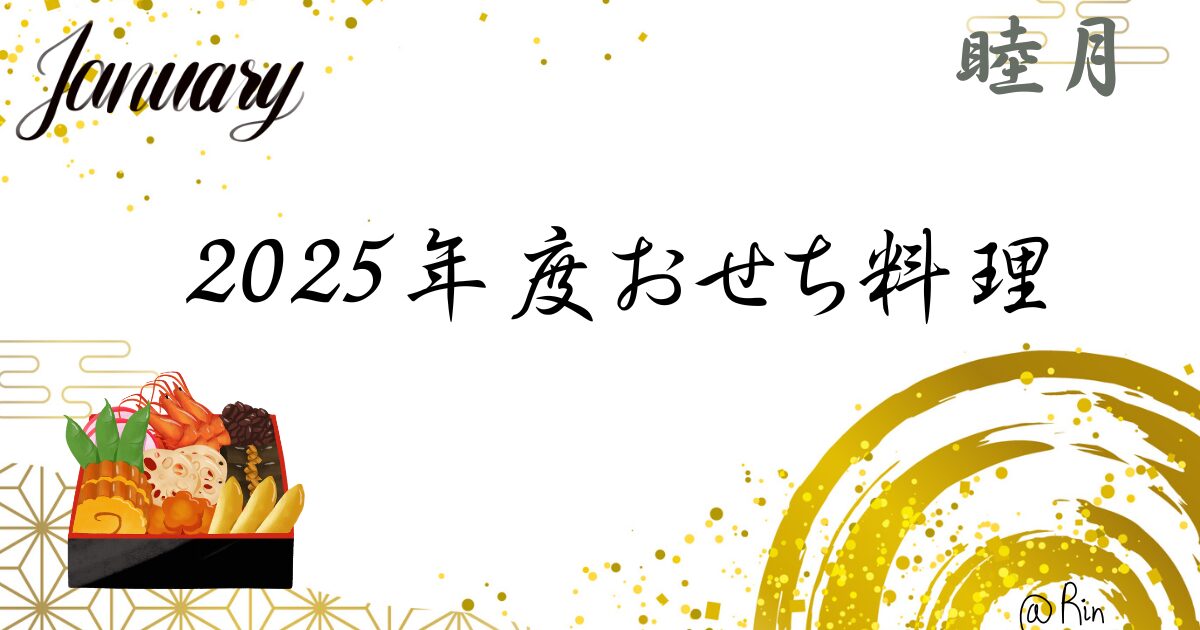
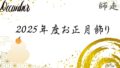

コメント