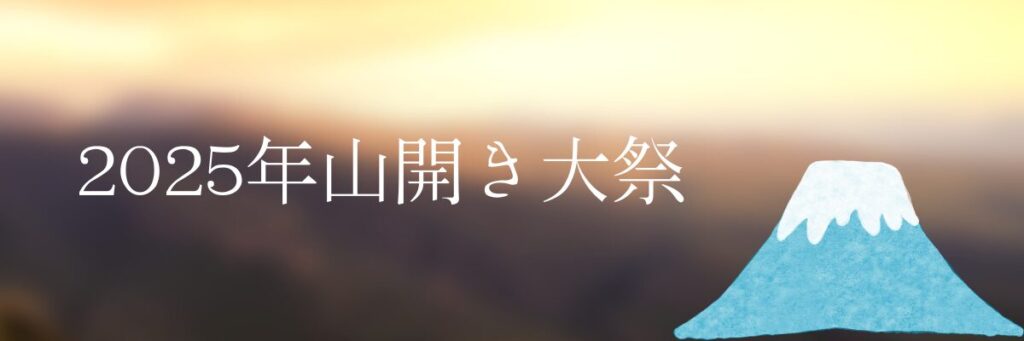
このブログは、四季折々にある日本の行事や日々の生活を愉しむコツをご紹介しています。
私は、四季の行事など全く興味がありませんでした。それでも、何も支障はなかったのですが、結婚した後、子供の成長と共に色々なことを経験するたびに自分が何も知らないことを実感しました。このままでは、どれが正解なのかわからない。子供にきちんと教えることも出来ない。親として情けないと思い、少しずつ勉強を始めました。私が知らなかったように、もし知りたいと思っている人のきっかけになればいいなと思います。四季折々の日本の行事を愉しみましょう。
今回は、『山開き大祭』です。
富士塚は知っていますか?

山は、山そのものを神聖なものとする山岳信仰から霊的な力をつける修行の場所とされていました。
山は、庶民には立ち入ることが出来ない神聖な場所でしたが、江戸時代に一定期間のみ『山開き』がされました。そして、庶民の間で富士詣(ふじもうで)が大流行しました。
しかし、富士山に登るのは大変なことだったので、市中に分霊されて祀られた富士権現に参り、『富士塚』(ふじづか)という人工の富士山に登りました。
特に有名なのが、浅草の富士浅間神社(東京都・台東区)や、駒込富士神社(東京都・文京区)などが有名です。今でも例大祭が7月1日の「山開き」に行われ、縁日や植木市などが行われます。
登拝といい、富士山の御神徳を拝しながら登山することを大切にされていました。
都内にも、たくさんの富士塚があります。富士塚に登ることで、「富士登山をしてお浅間さんにお詣りした」ことになります。授与品として”麦わら蛇”を購入できる所もあります。
江戸時代、富士山の『山開き』には、富士塚へ多くの人が参詣に訪れ、火事の多かった市中では「火防」として、疫病が流行した農村では「疫病除け」として、この蛇を買い求めました。水の守り神として、台所などのできるだけ水道の蛇口に近いところに飾って願ったようです。
富士塚には、様々な種類があります。
今回は、『小野照崎神社』『駒込富士神社』に行きましたので、ご紹介します。
小野照崎神社の富士塚です。

小野照崎神社をご紹介します。
852年(仁寿2年)、篁公が御東下の際に住まわれた上野照崎の地に創建され、寛永寺の建立とともに現在の地に遷されました。
江戸後期には、 学問の神様である菅原道真公(すがわら みちざね)も回向院より御配神として当社に遷され、境内にある末社を含めると、 15柱もの神様がお祀りされています。天明2年(1782)に築かれた富士塚「下谷坂本富士」。富士山に誰もが行けるわけではなかった時代、その霊験あらたかな姿を伝えるべく作られた直径は約15m、高さ約6mのミニチュアの富士山。一合目から順に十合目まで記されており、南無妙法と書かれた石碑や修験道の開祖である役小角の尊像も残る等、神仏習合の名残が見て取れます。先人の山守りの知恵によって今も当時の荘厳な姿を残しており、国の重要有形民俗文化財に指定されています。
毎年、夏越の大祓と富士山の開山に合わせた6月30日と7月1日の2日間に限り、一般の方々に開放されています。「不二(ふたつとない)」「不尽(つきることがない)」などがいわれとされる富士山。今もその霊験あらたかな神性を求め、多くの方々が富士塚に訪れます。(HPより抜粋)
6月30日には、山開きの前に多くの氏子さん方が参加されご祈祷が行われます。
その後開門され、宮司さんを先頭でお祓いをしながら富士塚に登り、頂上で富士山の方角に向き、「二礼二拍手一礼」をして願掛けをします。
その後を氏子さんたちが続いて富士塚を登り、最後に一般の私たちが登ることが出来ます。
富士塚に登ることが出来るのは、年に2日、6月30日と7月1日だけです。貴重ですね。
私は何度か登っていますが、やはり毎回神聖な気持ちになります。
「下谷坂本富士」は、富士山の溶岩で作られているため、溶岩を持ちながら進んでいきます。
手すりなどもありませんし、段差が大きいところや滑りやすいところもありますので、滑りにくい靴と動きやすい服装がいいと思います。また両手があいている方がより安心です。
※「二礼二拍手一礼」は、日本の神社で一般的な参拝作法です。まず二回深くお辞儀をし、次に二回手を叩き(拍手)、最後に一回お辞儀をします。これは、神様への敬意を表すための作法とされています。
ちょうど、6月30日は『夏越の祓』の日に当たります。
『夏越の祓』は、今年の前半の穢れを祓い、清めてこれからの半年間の無病息災を願う神事のことで、 茅の輪をくぐり、人形に穢れを吹きかけ、穢れを祓います。
『富士塚登山』と共に『夏越の祓』も一緒にお詣りできます。

『夏越の祓』につきましは、下記のブログもご覧頂ければ嬉しいです。
駒込富士神社で、神竜を授与して頂きました。

令和7年「駒込富士神社山開き大祭」 は、6月30日・7月1日・7月2日に行われました。
「駒込富士神社」には、富士塚はありませんが、少し高さの高い石段を登ります。登るところと下る石段は別にありますので、ご注意下さい。
石段を登ると、浅間神社の本殿があり、お詣りすることができます。
そこで、「神竜(麦わら蛇)」と 「麦らくがん 」を購入することが出来ます。
「神竜(麦わら蛇)」は、江戸時代中期の宝永年間の頃、江戸で疫病が蔓延した際に麦わら蛇を持っていた家には疫病を患う人がいなかったことから、疫病除けの縁起物として授与されてきました。蛇が枝に巻き付き舌を出している形をしており、「神竜」と呼ばれ現在に至ってます。台所の水回り付近に掛けてお祀りをします。頒布数に限りがありますのでお早めにお求め下さい。
「麦らくがん 」は、大祭日のみ販売される名物菓子で、麦粉で作ったらくがんです。雪化粧をした富士山の形をしており、1袋に約30個入っています。こちらも数に限りがございます。
なぜ麦の縁起物なのか ?
『文京区神社史』によると、神社周辺が農地だった頃、富士塚の上から麦畑が見えていたと述べていることからこの周辺にて麦を生産していたことがわかります。(HPより抜粋)

「駒込富士神社」は、「駒込天祖神社」の中の1つの神社です。
「駒込天祖神社」は東京都文京区本駒込に鎮座し、天照大御神(アマテラスオオミカミ)をご祭神としておまつりしている神社です。
「駒込富士神社」は、大祭の時には屋台も出てとても賑わいます。
私も、「神竜(麦わら蛇)」と「麦らくがん 」を購入しました。
「神竜(麦わら蛇)」は、以前のものをお納めし、新しいものを台所に飾りました。
「麦らくがん 」は、お話を伺うと地域の方が作っていてたくさんは作れないそうです。
落雁(らくがん)は、米や豆、蕎麦、栗などから作った澱粉質の粉に水飴や砂糖を混ぜて着色し、型に押して固めて乾燥させた“打ちもの”と呼ばれる干菓子のことです。仏壇にお供えする菊の花のイメージが強いですね。
「麦らくがん 」は、好き嫌いは分かれるかもしれませんが、麦が香ばしくて食べやすかったです。
富士山をモチーフにしているので、縁起物としてお土産としても喜ばれそうです。
まとめ

富士塚は現在も関東地方を中心にたくさん残っているそうです。大きさも見た目も様々ですが、それぞれの土地で富士山と同じように「山開き」「山仕舞い」などの行事も行われています。
富士塚は地域で維持されてきましたが、やむを得ない移転や祭りが縮小されたりするなどで「山開き」を行う神社も少なくなっているようです。
日数は限られていますが、機会があれば富士山を富士塚を見てほしいと思います。昔の人が富士山をどれだけ大切にしているかを知ることができます。そして、今もなお変わらない富士山の偉大さも感じられます。
来年は、また違う山開きを体験してみたいと思います。
最後まで読んで下さりありがとうございました。
「山開き」は、入山を許す日です。も合わせてご覧頂ければ嬉しいです。
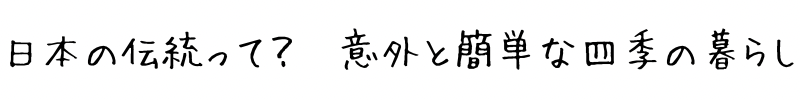



コメント