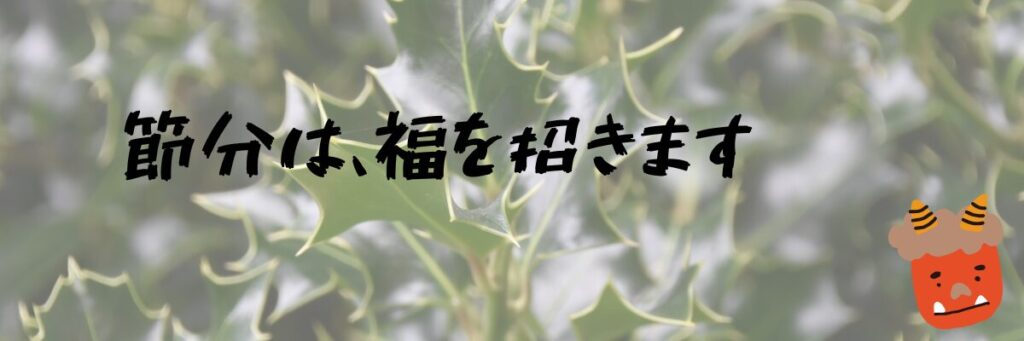
こんにちは、名越凜です。
このブログは、四季折々にある日本の行事や日々の生活を愉しむコツをご紹介していきます。
私は、四季の行事など全く興味がありませんでした。それでも、何も支障はなかったのですが、結婚した後、子供の成長と共に色々なことを経験するたびに自分が何も知らないことを実感しました。このままでは、どれが正解なのかわからない。子供にきちんと教えることも出来ない。親として情けないと思い、少しずつ勉強を始めました。私が知らなかったように、もし知りたいと思っている人のきっかけになればいいなと思います。四季折々の日本の行事を愉しみましょう。
今回は、『節分』についてです。
節分とは?

『節分』とは、「季節」を分けるという意味です。また、雑節の1つです。
本来、季節を分ける日は1年間に4回あって、春夏秋冬それぞれに始まりの日が決められています。
春夏秋冬、それぞれが始まる日の前日のことを『節分』といいます。しかし、太陽の動きによって決まるので、毎年同じ日とは限りません。
また、季節の変わり目には邪気(鬼)が生じると考えられており、その鬼を追い払い、無病息災を願う儀式です。
2025年は、2月2日(日)で、恵方は西南西です。 2026年は、2月3日(火)で、恵方は南南東です。
雑節とは?

雑節とは、五節供、二十四節気以外の移り変わりの目安になる日の総称です。
詳しくは「雑節は知っていますか?」をご覧ください。
二十四節気は中国腕作られた暦のため、農業に従事する人が十分に季節の変化を読み取れないいことから、その頬所をするために考えられた日本独特の暦です。
「五節供」とは、人日(じんじつ)の節句・上巳(じょうし)の節句・端午(たんご)の節句・七夕(しちせき)の節句・重陽(ちょうよう)の節供のことを言います。
詳しくは、「五節供は、特別な日です」をご覧ください。
豆まきはしていますか?

皆さんの家では「豆まき」をしますか?
「豆まき」は、節分の日に鬼を追い払い、福を招くために炒った豆をまく風習です。
「鬼は外、福は内」と言いながら、鬼に豆を投げますね。親子で「豆まき」をする方も多いのではないでしょうか。
『豆まきの由来』は、「追儺(ついな)」という鬼払いの儀式が原型で、「追儺」は冬の邪気を祓い、春を迎える行事です。
- 豆まきで病気や災害などの邪気を追い払います
- 健康や豊年を願います
【豆まきの仕方】
- 鬼が戸口から入るのを防ぐため、「柊(ひいらぎ)の枝に焼いた鰯(いわし)の頭を串刺ししたもの」を門や玄関に吊るします。
- 玄関、ベランダ、窓などすべての窓や扉を開けます。
- 年男・年女は桝に入れた福豆を手にして、玄関から各部屋を回ります。
- 「鬼は外、福は内」と2回ずつ繰り返し声をかけながら豆をまきます。
- 豆をまき終わったらすぐに窓や扉を閉めます。
1は、冬を追い出すために行います。焼いた鰯は臭みが強く、柊はトゲがあって鬼が嫌うと言われています。
「豆まき」に使う豆は炒った大豆が一般的ですが、殻付きの落花生を使う所もあります。最近では、掃除が大変なことや食べ物を無駄にしないという観点から、袋に入った大豆を使うことも多いです
まとめ

節分には、神社やお寺などで有名人が投げる豆まきをよく見かけますね。
家でする豆まきとは、また違いますが一気に冬を追い出して春が訪れそうですね。
福豆は、神社やお寺などでも買うことが出来るので、私は神社やお寺など毎年、色々な所で購入しています。ご利益もありそうですよね。
どんな方法であれ、福を呼び込んで、1年間無病息災で過ごしたいですね。
最後まで読んで下さりありがとうございました。
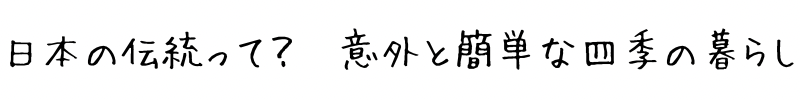


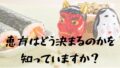
コメント