
こんにちは、名越凜です。
このブログは、四季折々にある日本の行事や日々の生活を愉しむコツをご紹介していきます。
私は、四季の行事など全く興味がありませんでした。それでも、何も支障はなかったのですが、結婚した後、子供の成長と共に色々なことを経験するたびに自分が何も知らないことを実感しました。このままでは、どれが正解なのかわからない。子供にきちんと教えることも出来ない。親として情けないと思い、少しずつ勉強を始めました。私が知らなかったように、もし知りたいと思っている人のきっかけになればいいなと思います。四季折々の日本の行事を愉しみましょう。
今回は、『端午の節句』についてです。
端午の節供は、五節供の1つです

『端午の節句』は、五節供の中の1つです。男の子の節供や子供の日としても知られています。
ところで、五節供はご存知ですか?
五節句とは、1年間で5つの季節の節目を祝う行事です。節句の由来や歴史はそれぞれ異なり、時期に合わせて特別なお祝いや行事食(歳時食)が食べられます。
- 1月7日 人日(じんじつ)の節句 七草の節句
- 3月3日 上巳(じょうし)の節句 桃の節句・ひなまつり
- 5月5日 端午(たんご)の節句 菖蒲の節句・こどもの日
- 7月7日 七夕(しちせき)の節句 星祭り・たなばた
- 9月9日 重陽(ちょうよう)の節句 菊の節句
五節供につきましては、『五節供は、特別な日です』も合わせてご覧頂ければ嬉しいです。
「節句」は、本来『節供』という字が使われていましたが、現在では、「節句」のほうが多くが使われています。
本来は同じ意味ですが、『節供』の「節」は季節の節目に当たる特別な日に、「供」は供物のことで神様にお供え物をすることを表しています。
端午の節句とは?

「端午の節句」は、旧暦で初めての午の月に当たる5月に今では定着しています。
かなり以前、奈良時代から「端午の節句」はあったようです。
奈良.平安時代は、菖蒲やヨモギが魔を祓うと言われていたことから、菖蒲の薬のくす玉を吊るしていました。菖蒲は、強い香りを発するため毒気を祓うと信じられていました。
鎌倉時代になると、菖蒲を「尚武(武士を重んじること)」と見立てて武家の行事として定着しました。庶民の間では、菖蒲湯や菖蒲酒が一般化で、魔除けの意味もあったようです。
江戸時代になると重要な行事として幕府の「式日」に制定されました。大名や旗本などは、「ちまき」を献上して将軍にお祝いを述べるため、式服の帷子紋付(かたびらもんつき)に長袴姿で江戸城に出向いていました。
※式目とは、「武家時代、法規・制度を箇条書にしたもの」です。決まり事や命令などを箇条書きにしたもののことをいいます。
しかし、5月5日は、夏服への衣替えの日で、単衣の武士たちは「帷子(かたびら)」という夏用の装束で登城しました。
「端午の節句」が男の子の節句となったのは、江戸時代以降です。
将軍家のお世継ぎの誕生を祝って織がいくつも上がり、作り物の兜や薙刀などもたくさん立てられました。それがのちに庶民にも広がっていきます。
「端午の節句」には、出世魚のブリや「勝男」にかけてカツオが食べられました。行商人が江戸の町で売り歩いていたと言われています。
鯉幟(こいのぼり)は、江戸時代の中期から見られましたが、家紋の入った幟(のぼり)と1本の竿に1匹の鯉幟を飾っていました。
しかし、1本の竿に何匹かこいのぼりがはためく姿は、明治以降に見られるようになります。
まとめ

鯉幟はむかし、家紋を入れた幟(のぼり)と、一匹の鯉を竿に飾ることから始まりました。
その後、吹き流しや鯉も増えていきます。
吹き流しには、「吹く風に逆らわず、流れに従って生きていけ」・「物や思いを腹に溜め込むな」という、思いがこもっているそうです。
五色の色は、儒教の「五常」から来ています。
- 仁 例えば、人に喜ばれることを大切にする生き方
- 義 例えば、人の恩を忘れず、恩に報いる生き方
- 礼 例えば、清潔に身だしなみを整え、言葉を大切にし、けじめのある態度をとる生き方
- 智 例えば、偉人の本を読んで生き方を学ぶ、勉強をしっかりする生き方
- 信 例えば、嘘をつかない、裏切らない生き方
どれくらいの人が子供の成長を願い、鯉幟をあげたのでしょう。その気持ちは今も昔も変わりませんね。
たくさんの子供が、健やかに大人になれるように願います。
最後まで読んで下さりありがとうございました。
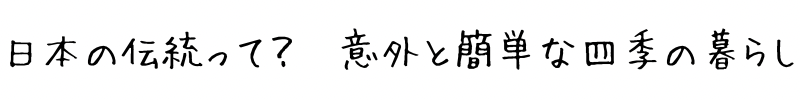

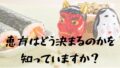

コメント