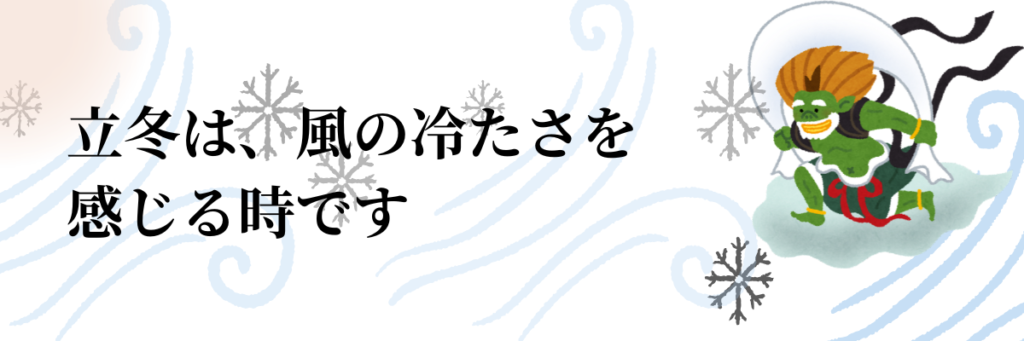
こんにちは、名越凜です。
このブログは、四季折々にある日本の行事や日々の生活を愉しむコツをご紹介していきます。
私は、四季の行事など全く興味がありませんでした。それでも、何も支障はなかったのですが、結婚した後、子供の成長と共に色々なことを経験するたびに自分が何も知らないことを実感しました。このままでは、どれが正解なのかわからない。子供にきちんと教えることも出来ない。親として情けないと思い、少しずつ勉強を始めました。私が知らなかったように、もし知りたいと思っている人のきっかけになればいいなと思います。四季折々の日本の行事を愉しみましょう。
今回は、二十四節気の『立冬(りっとう)』についてです。
立冬とは?

『立冬』とは、風の冷たさを感じる頃で、家でも寒さを感じて「こたつ」などの暖房器具準備を始めます。
二十四節気では、11月7日〜11月21日頃の18日間です。
『立冬』は、二十四節気の「冬」の6つの中の1つです。
- 立冬(りっとう) 11月7日~11月21日頃
- 小雪(しょうせつ) 11月22日~12月1日頃
- 大雪(たいせつ) 12月7日〜12月21日頃
- 冬至(とうじ) 12月22日〜1月5日頃
- 小寒(しょうかん) 1月6日〜1月20日頃
- 大寒(たいかん) 1月21日〜2月3日頃

- 山茶始開(つばきはじめてひらく) 初候 11月7日〜11月11日頃 山茶花(さざんか)の花が咲き始める頃です。昔からサザンカとツバキはよく混同されてきたため、「山茶始開」と書いて、「つばきはじめてひらく」と読まれました。
- 地始凍(ちはじめてこおる) 次候 11月12日〜11月16日頃 大地が凍り始める頃。地中の水分が凍ってできる霜柱がみられるようになることです。
- 金盞香(きんせんかさく) 末候 11月17日〜11月21日日頃 スイセンの花が咲き、よい香りを放つ頃。通常、スイセンは「水仙」と書き、キンセンカという別の花もありますが、 金盞は、「水仙」の異名です。

「山茶花(さざんか)」の花言葉は、困難に打ち勝つ、ひたむきさ。
晩秋から初冬にかけて花をつける「山茶花」は、椿と似ています。
見分けるコツは、花びらの散り方です。散る時に花びらがひらひらと落ちるのが、山茶花です。花首からポロッと落ちるのが、椿です。
山茶花は、地面を赤やピンクに染めます。
立冬の行事とは?

- 11月7日 亥の子祭り 2025年11月2日
西日本では旧暦10月の最初の亥の日に開催される収穫祭です。大豆・小豆・ささげ・胡麻・栗・柿・糖の7種を混ぜた「亥の子餅」を食べ、亥の子づきをしたり、こたつ開きをします。 - 11月7日 炉開き 2025年11月8日
茶道において、夏の間の風炉を撤し、炉を開く日です。11月より翌春5月まで、半年間、炉による茶の湯が行われます。 - 11月15日 七五三 2025年11月15日
数えの年齢で3歳・5歳・7歳の男の子と女の子が神社に詣で、神様に成長を報告する日です。着物や袴姿でお詣りして千歳飴を頂きます。
亥の子祭りと亥の子餅

亥の子祭りとは、旧暦の10月(亥の月)の亥の日に、無病息災や子孫繁栄を願う神事や行事です。中国の民間信仰に由来し、多産なイノシシにあやかることで願いが叶うとされています。
有名なのは、京都の『護王神社』で、平安京の建都に貢献された和気清麻呂公(わけのきよまろこう)をお祀りしている神社です。
亥子祭は平安時代に宮中で行われていた年中行事「御玄猪(おげんちょ)」にちなんだ祭り。
亥の月(旧暦10月)の亥の日、亥の刻に餅を食べると病にかからないと考えられた中国の民間信仰を起源とする。亥子餅をつく儀式の後、平安装束の一行が京都御所へ餅の献上に行き、参加者はイノシシの陣羽織姿でそれに従う。神社に戻った後は亥子餅が一般の参拝者にもふるまわれ、無病息災を祈願する。護王神社のHPより抜粋 https://www.gooujinja.or.jp/
亥の子餅(いのこもち)は、平安時代の宮中儀式から続く歴史あるお菓子です。旧暦の亥の月(現在の11月)の最初の亥の日・亥の刻に食べると無病息災や子孫繁栄が叶うとされてきました。
また、亥の子餅は11月に行われる茶道の「炉開き」に欠かせない和菓子です。
茶道で11月に行われる「炉開き」とは、5月から10月まで閉じていた「炉」に初めて火を入れる日のことを言います。 「炉」は、お湯を沸かす所です。節目の行事です。
「亥」は中国の陰陽五行説では、水の性質をもつことから火を防ぐと考えられ、お茶席では亥の日に炉開きやこたつ開きをする風習ができたとされています。
そのため、この時期のお茶の席では火事にならないよう願いを込めて「亥の子餅」を食べる習慣が始まったと言われています。
まとめ

『立冬』の頃から季節は冬になります。一段と寒くなりましたね。
茶道の「炉開き」もありますが、江戸時代には、「こたつ開き」も行われていたようです。
武士は、旧暦10月の初の亥の日、庶民は2回目の「亥」の日に、こたつを出しました。
そろそろ、寒さのための準備を始めなければなりません。この時期に、大掃除をするのもいいかもしれませんね。師走の寒く、慌ただしい時期よりは良いようにも思います。
鍋やおでんなども美味しい季節になります。
内外から温めて、リラックスや風邪予防するのもいいですね。
七五三のことについては、こちらも読んで頂けると嬉しいです。
最後まで読んで下さり、ありがとうございました。
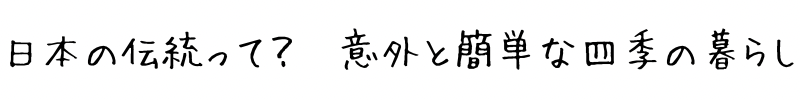
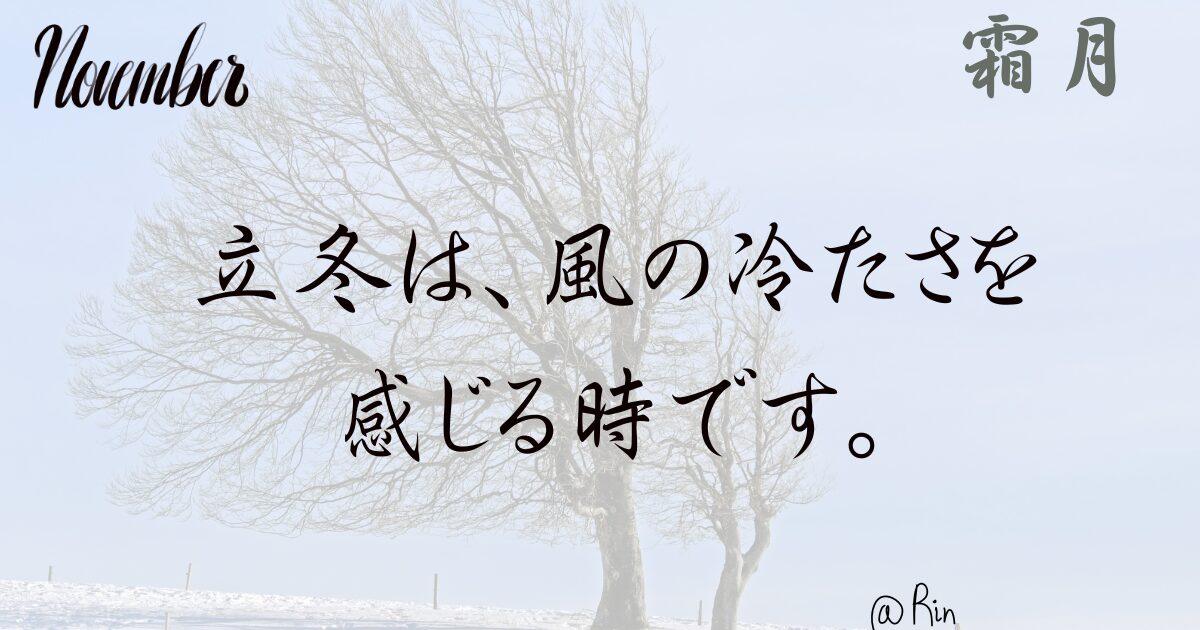
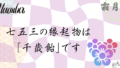
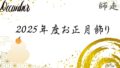
コメント